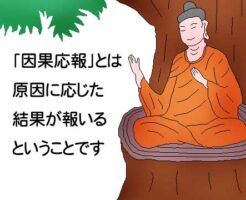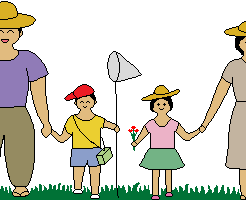最近は皆さんにいろんな供養をお願いされるようになりました。水子供養もそうです、母親の母性として忘れていても、ふとした時に思い出してしまうのが水子のことです。何かしてあげたい、何かしないといけない…こういう時の供養って高い […]
「2019年」の記事一覧(7 / 14ページ目)
因果応報とは-不幸が続く原因について
因果応報とは 因果応報とは仏教用語であり、物事には原因があって結果があり、原因に応じた報いを受けるということです。 因果応報は仏教用語である 私達はこの世で生きている時にも全ての事象に対して原因と結果があり、死後の世界で […]
亡き人に対して何をすれば良いか
人が亡くなるということについて幸不幸があるとしたら、寿命が尽きて亡くなる天寿全うということが最も幸せな亡くなり方であり、病気や事故、自殺などで亡くなる場合は不幸な亡くなり方ということになります。 事故で亡くなった方に関し […]
毘沙門天は神それとも仏?
毘沙門天は神それとも仏? 仏教寺院にも居られますし、七福神の宝船にも乗っていますが、意外と色んな所で活躍されているのが毘沙門天なのです。 仏教では四天王として北方を守る役目の多聞天と言われ、七福神の中では宝船に乗って船頭 […]
最後のお別れは必ずやってくる
墓じまいの時にお墓から取り出したお遺骨を合葬墓に納骨する時に拝んでいる様子です、衣を着けて読経することもあれば作業着に着替えて作業することもあります。 これまでは個別のお墓に居られたお遺骨も、後継者が居ないために合葬墓に […]
散骨供養とは
散骨とは遺骨を粉状にして自然の中に散布することですが、現代社会に於いては遺骨を合法的に捨てるということにも利用されていますし、葬送の儀として厳粛に執り行うことも出来ます。 遺骨を捨てるような散骨は無縁仏を増やすだけであり […]
老と病は共にやってくる
病草紙第2弾は「歯痛の男」です。この場面の右側には注釈があり、「男ありけり。もとより口の内の歯、皆揺ぎて、少しも、強(こわ)き物などは、噛み割るに及ばず。なまじゐに落ち抜くることはなくて、物食ふ時は、障りて耐えがたかりけ […]
病草紙-平安時代の眼医者は怖い
平安時代の奇病を画いたという「病草紙」は、平安時代末期から鎌倉時代初期に、土佐派の画家によって書かれた絵巻物です。 大和国に住む眼病の男はある日訪れた眼医者と称する男に目の治療をさせるが、針が良いだろうと針治療をして帰っ […]