目次
離檀とは

離檀とは先祖の供養や法事・葬儀などを行う菩提寺を金銭面で支える檀家を辞めることで、遠方に引越するなどで菩提寺との付き合いが無くなるような時に離檀届を菩提寺に申請します。
菩提寺とは

菩提寺とは宗旨に帰依した一家代々の法事・葬儀や先祖の供養を行う寺院のことで、御布施や寄付などの金銭面で支える一家のことを檀家と言います。
菩提とはサンスクリット語のボーディ(bodhi)の音写であり、悟りを意味し、悟りを得て極楽浄土に往生することでもありますから、菩提寺とは亡き人を極楽往生させるために供養している寺ということにもなります。
つまり檀家の御先祖を成仏させるために法事や葬儀を行い、自坊では毎日檀家の御先祖の供養を行っているのが菩提寺の役目なのです。
亡き人に引導を渡すというのは、亡き人の手を引いてを浄土に渡して差し上げることなのです。
全ての寺院が菩提寺と檀家の関係にある訳でなく、祈願を行う信者が参拝する祈願寺や、四国八十八箇所・西国三十三観音などの巡礼者が参拝する巡礼寺など様々な形態の寺院があります。
一般的には寺院の敷地の中に檀家の墓地があることが多く、離檀する時には墓じまいして墓地を更地にし、遺骨を改葬して引き上げることが必要になってきます。
檀家とは

供養を通して菩提寺と僧侶を金銭的に支援する人のことで、菩提寺の宗旨を信仰し、家には宗旨の形式の仏壇を置き、墓地もその宗旨の形式にします。
江戸時代の檀家制度の流れを引き継いで檀家になっていることが多く、先祖代々が菩提寺の檀家であればその子孫まで檀家であり続けるような仕組みになっています。
菩提寺の檀家は一つのまとまった組織として運営され、各檀家は年会費を支払い、地区ごとに檀家の代表である総代が選出されて定期的に総代会を開いて檀家の転入・転出などの報告をし、寺院の運営を確認します。
寺院墓地の区画を一般向けに販売しているような寺院では、墓地の区画を購入した時点で檀家の扱いになっていることがありますので、注意が必要です。
離檀の理由
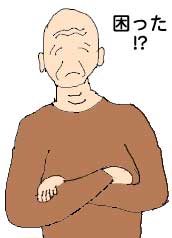
寺院から離檀する理由は大きく分けて引っ越しなどでやむを得ない場合と、寺院との関係が悪い或いは住職が気に入らないなどの理由で離れたい場合の2つがあります。
引越のため

引越はやむを得ない理由ですから、役所に出す転出届と同様に寺院に対しても事務的に申請できますのであまり悩む必要なく、離檀の理由に関してのトラブルになることは少ないです。
お布施が高い

離檀の理由で意外と多いのがお金の問題で、
- お布施が高い
- 戒名料が高い
- 寄付金が高い
など何でも高いから出せない、出したくないということです。
自分の父親の代には商売をしていて羽振りが良かったので高い戒名を貰っていたが、自分の代になって仕事の収入が少ないので以前と同じようには出せないのに、戒名のランクは下げることが出来ないと言われて困っている…
中には「お布施はお気持ちでどうぞ」と言っておきながら実際には目の前で中を開け「これでは少ない」と言われるようなこともあり、とにかくお布施という曖昧なお金に関するトラブルが絶えません。
今の不安定な世の中で生活に困っている人は増え続け、わずかな年金だけで生活している人もたくさんいる中で、高いお金を出したくないから檀家を辞めたいというのは正直な気持ちかもしれません。
住職が尊敬できない

「あそこのお寺の住職は…」近所同士の世間話で出てくる話題として寺院の住職の日頃の素行が悪く、
- 遊んでばかりいる
- 贅沢三昧
- 上から目線で物を言う
- お金のことばかり言う
- 人の話を聞かない
- 寺院のお勤めをしない
- 読経を間違える
- 御布施の金額によって読経の長さが違う
などのうわさ話が流れるのは皆から快く思われていない証拠であり「自分達が出した御布施で遊んでいる」などと言われるようになったら尊敬されていないということで、こういった事が原因で離檀したいと思う人も多いのです。
寺院の住職は仏に仕え法を説くことが本来の仕事であり、日々檀家の先祖の供養をしてくれているという感謝の気持ちで皆に支えられているのですから、本来するべき仕事を忘れてしまうようでは人々から尊敬されることもなく、そういう寺院から離れたいと思われても仕方ありません。
納骨を許可しないと言われた
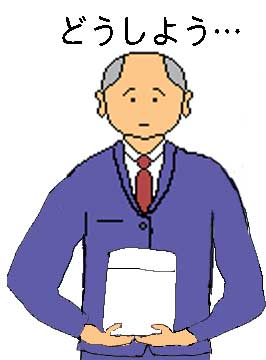
都会に出て家を持った人達が故郷の両親を呼び寄せて一緒に暮らしていたのも束の間のことで、やがて共に亡くなって都会で葬儀をしてから故郷の寺院に納骨したいと連絡したら、自分の所で葬儀をしていないから納骨出来ない、どうしても納骨したいのならこちらで戒名を付け直し、葬儀をもう一度こちらでやり直して下さい、と言われる事例が後を絶ちません。
地方の寺院では檀家の数が減って運営が苦しくなっているのです。
都会に出た者としては止むを得ず都会で葬儀をした訳であって、相当なお金も使っているのに、もう一度やり直せと言われても出来る訳ありません。
もうこの際菩提寺とは縁を切ろうと決心するのは、このような事例があるからです。
離檀の方法

寺院から離檀するためにはまず寺院に行って離檀の旨を伝え、離檀届に署名捺印し、敷地内に墓地がある場合には墓地返還届や改葬許可申請書などが必要になりますので、まずは離檀の相談に行くことから始めます。
寺院敷地に墓地を所有していない場合

檀家の扱いになっているが寺院に墓地を所有していなが、引越する或いは後継者が居ないなどで離檀したい場合には、まずは寺院に相談に行きます。
引越する場合には寺院には離檀を引き留める正統な理由はありませんので、スムーズに話が進むはずです。
後継者が居なくて古くからの檀家である場合には引き留められる可能性が大です。
寺院との関係が良好であって合葬墓の施設が良心的な費用で利用出来るのなら、自分の葬儀或いは今あるお墓の墓じまい・改葬についても相談してみましょう。
寺院敷地に墓地を所有している場合

檀家の扱いになっていて寺院に墓地を所有している場合は寺院との金銭的なトラブルが最も多く、莫大な墓じまいの費用や離檀料を請求されることがあります。
特に石材店が指定されている場合には合い見積もりを取ることが出来ませんので、最初からいきなり高額の墓じまい費用を提示され、支払うのが嫌ならやりません、という態度をとられることがあります。
特に住職の態度が気に入らないなどの理由で離檀しようとすると、いきなり大ゲンカになったりします。
寺院の敷地の中では寺院の取り決めに従う規則がありますので、外部の者が口出しした所で「それは決まりですから」と言われて終わりになり、別途お金が掛かりますが弁護士などが同席すると話がうまくいくことが多いです。
寺院墓地であっても墓じまいの業者は何処でも構わないという寺院もあります。
そういう時には…やすらか庵の墓じまい無料見積り
墓じまい相談は代表清野徹昭がお答えします…墓じまい相談専用電話043-228-1480
離檀料について

離檀料については各寺院によって対応が違い、不要のこともあれば、何十万円、何百万円ということもあります。
離檀料の寺院側からの名目としてはこれまで長い間御先祖の供養を続けてきた訳ですから、これまで供養を続けてきたお礼は当然支払うべきと考えられています。
しかし檀家の側からすると供養の旅に御布施は出しているのだから、最後だからと言って特別に出す必要は無いと考えるのです。
寺院側からすると去る者については取るだけ取れということでしょうけれど、離檀料などは本来は寺院が決めるものでなく、お礼というものは去るものが気持ちとして出すものです。
寺院に相談に行く場合には決してこちらから離檀料は幾らですかなどを聞いてはいけません。
寺院側から言われなければ「その他にお支払いするものは何かありますか」と聞けば良いだけです。






