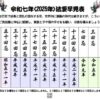自灯明法灯明
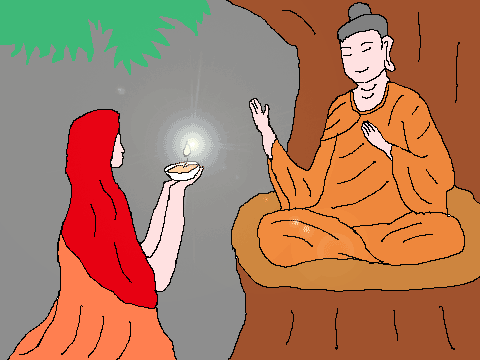
釈迦は説法の旅を終えて80歳になった頃、パーヴァー という場所で鍛冶屋のチュンダに法を説き供養を受けた後、マッラ国のクシナガラの近く、ヒランニャバッティ河のほとりのサーラ樹の下で入滅しましたが、最後に弟子に残した言葉が「自灯明法灯明」でした。
自灯明法灯明の由来
入滅が近くなった釈迦がもし本当に居なくなってしまったら、自分達はどうしたら良いだろうかと思った弟子のアーナンダは釈迦に対して「師が居なくなったら何を頼りにして生きていけば良いのか」と尋ねたその答えが「自灯明法灯明」でした。
釈迦もこの世に生きている限りは生身の人間の体をまとっているので、歳を取れば思うように動かなくなり、病気も治りにくくなってしまいます。
釈迦は最後に鍛冶屋のチュンダに法を説き供養を受けたが激しい腹痛を訴えていましたが、自らの運命をも悟っていたのでしょうから、極めて冷静な仏としての対応をされています。
たとえ自分がどのような状況であろうとも、常に正しい法を説いていたのです。
自灯明法灯明の意味
「自灯明法灯明」は「他を頼りにすることなく自分を灯明の明かりとして進み、正しい法を灯明の明かりとして進みなさい」という事です。
釈迦が居なくなってしまうことを心配したアーナンダに対して、私が居なくなっても、私を頼りにするのではなくて、自分自身を頼りにし、そして正しい法を頼りにしなさいということなのです。
仏になった釈迦であっても何時までもはこの世の世界に居ることは無いのだから、それでも仏法として説かれた正しい法は残り続けるのだから、それを頼りなさいという事は、後世の私達に言っていることでもあるのです。
灯明の歴史
今の時代のように電気の無かった時代には夜になれば真っ暗になるのは当然のことで、縄文時代から竪穴式住居の家の中の囲炉裏で火を焚き、その火で煮炊きや明かりとして、或いは暖を取っていたのですが、動物が火を怖がることから、動物除けとしての役割もあったことでしょう。
太古の昔の私達の祖先はおそらく外でも火を焚いていたのでしょうし、様々な利用の仕方をしていたのではないかと思います。
今の時代の柴燈護摩やお焚き上げ或いはどんど焼きのように宗教的な役割もあったことでしょう。
油の中に芯を入れて灯明として使うことが普及したのは歴史的に見ても近年になってからのことで、油を大量に生成するための方法が確立されていなかったことや、出来上がった油が高価だったことなどの理由で一部の裕福な階級の人しか利用することが出来ませんでした。
明治時代には都会にガス灯が灯ったりしますが、庶民の家ではイワシの油の灯明などが安価に手に入っていたようです。
寺院の灯明
寺院の灯明としての最古の遺跡としては7世紀の山田寺(奈良県桜井市)の下層から出土した灯明皿とされていますが、どのような油を使っていたのか、本当に使われていたのかは分かりません。
高価で手に入りにくいものだけに、豪華で華やかな寺院で使われていたことは十分に考えられます。
寺院の灯明は真理の仏の世界を照らし出すという目的と、法を守り伝えるという目的があります。
今でも高野山奥の院燈籠堂の「消えずの火」は弘法大師空海の灯した火とされ、天台宗比叡山延暦寺の「不滅の法灯」は伝教大師最澄が灯した火とされて、消えることなく灯され続けられています。
これらの火を守ったのは、長い歴史の中でそれぞれの時代に関わった歴代座主と教団を支えた僧たちのたゆまぬ努力の賜物なのです。
灯明と仏教

人間は一人でいると寂しいという社会的動物なのであり、本来は群れを作って皆と同じように行動するのが最も安全で安心な方法ですから、自分で行く先を決めるということが苦手で、誰かに示してもらった方が良いという意味では釈迦はカリスマ的な存在だったのです。
真理を悟った人が過去にも現在にも一人しか居ないのですから、釈迦が仏としての灯明を照らしてくれることで私達は行き先を確かめることが出来るのです。
しかし頼りの釈迦に「自灯明法灯明」と言われてしまったらもう自分を頼りにするしかありません。
結局は修行をするにも、死後の世界に行くにも最終的には自分で行かなければならないのです。
死後の真っ暗闇の世界にでも一人で向かわなければならないのです。
しかし現世では法の灯で照らしてくれると共に、死後の世界も案内してくれるという信仰が十三仏信仰であり、順番として不動明王の次に釈迦如来が来る所以なのです。
今の時代は灯明が簡単に手に入りますし、ロウソクなども安いですから是非一度良い香りのするお香と共に灯してみて下さい。
私達の世界の周りは宇宙も含めて暗黒の世界ですが、仏の世界には灯明があるのです。
灯明の有難さが分かってくることでしょう、そして感謝の気持ちが湧いてくることでしょう。